
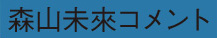
あまりに膨大な情報が同時に行き交い、正誤の判断すらままならない。そんな現代。
身体表現、そして音楽でさえも情報を伝達するための一つの「ことば」だとして。
この舞台の上に散りばめられたありとあらゆる「ことば」でもって、バベルの塔にまた人々は集結することができるのだろうか。
しかしそれはまた、何を意味することなのか。
これはダンスパフォーマンスでも演劇でもコンサートでもない。
では何だ。一緒に考えてくれませんか?
森山未來
現在、平成25年度海外派遣型「文化交流使」としてイスラエルを拠点に活動中
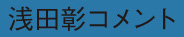
『BABEL』はダンスの最前線に立つ。必見!
ピナ・バウシュが世を去り、ウィリアム・フォーサイスの関心が大規模な舞台作品から離れたかに見えるいま、ダンスの最前線が見えにくくなってしまった。とくに日本では、時間が何十年も昔に巻き戻されたかのように、古色蒼然たる舞台ばかりが目につく。いったいどうしたことだろう、世界ではシディ・ラルビ・シェルカウイという異色の才能が確実にダンスの未来を切り開きつつあるというのに。
むろんシディ・ラルビの仕事は日本にも紹介されてきた。Bunkamuraでの日本人とのコラボレーションを想起する人もいるだろうが、私の記憶に鮮やかなのは、むしろもっと前の作品だ。
たとえば、びわ湖ホールで上演された『D'avant』(ダミアン・ジャレと共同振付・演出)は、現代の荒廃した都市を思わせる舞台で彼を含む4人のダンサーが中世歌謡を歌いながら踊る、墓石の下に入ってなお歌い続けるという、実にスリリンングなパフォーマンスだった。
あるいは、さいたま芸術劇場で上演された『zero degrees(ゼロ度)』。第3世界の出入国管理エリアという高度に政治的な空間で彼とアクラム・カーンの2人がベケット的な不条理劇を演じ踊る。一種の分身としてアントニー・ゴームリーの等身大の人形が見事な効果を上げていたことも忘れがたい。
それを思い出すとき、ジャレとの共作でゴームリーが装置を担当する『BABEL (words)』への期待は高まるばかりだ。「バベル」すなわち「混乱」。それは現代の世界で多文化の衝突と合流の生み出す残酷にして豊饒な「混乱」であることだろう。ダンスの——いや舞台芸術の最前線に立つこれほどの話題作を見逃す手は絶対にない。